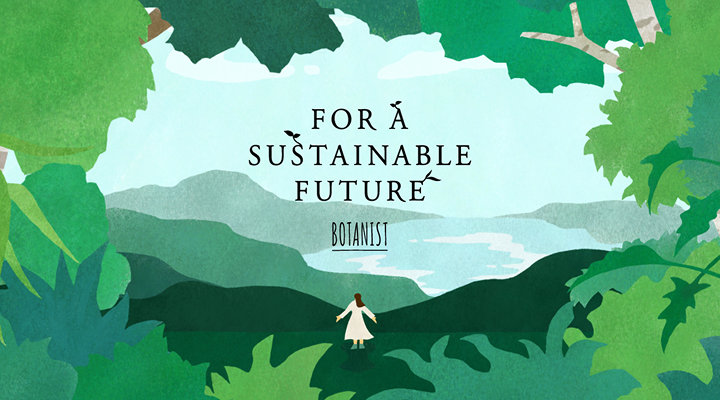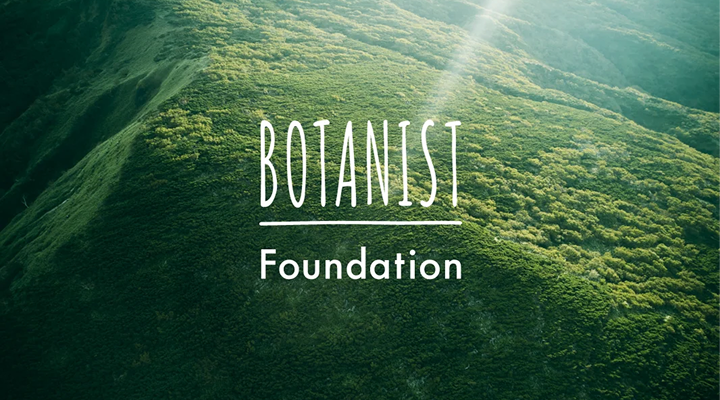SUSTAINABLE 19
街を植物園にする“インタープリター”って?樹木医・瀬尾一樹さんと、東京駅周辺を歩く
2023.12.04
都内近辺を舞台に、身近な自然の魅力を発信している瀬尾一樹さん。X(Twitter)では植物マニア「悟空」として、フォロワー10万人を超える人気を博しています(現在投稿はお休み中)。本業の傍ら、街中を歩きながら自然解説を行う「インタープリター」として活動中。今日はそんな瀬尾さんと一緒に、東京駅から皇居前まで歩いてみます。

人が行き交う東京駅で、足元に目を凝らす
9月上旬の昼下がり。ジリジリと日差しがそそぐ東京駅丸の内駅前広場に、瀬尾さんの姿がありました。
「暑いですね。今日はよろしくお願いします」
リュック姿の瀬尾さん。午前中は、別の場所でお客様をつれてインタープリターの活動をしてきたそう。月1で定期的に申し込むリピーターもいるといいます。
「では、さっそく行きましょう。まずはこの植え込みを見てみましょうか」
駅舎中央に位置する大きな松の木のふもと。植木に四角く囲まれたスペースを、瀬尾さんは覗き込みます。

「一見しっかり整備されているように見えますが、囲いの中はユートピア状態です。きのこも生えていますね。
じゃあ問題です。このあたり(以下写真の範囲)に、全部で何種類の植物があると思います?」

ものの数秒で数え上げる瀬尾さん。答えはなんと、8種類。
「エノキグサ、カタバミ、その横で地面を這っているのがハナイバナ。奥にあるのがトキンソウです。チチコグサやイヌワラビ、ドクダミ、ハルジオンも生えていますね」
それぞれの場所を、わかりやすく説明してくれました。
「一見ただの緑でも、いろんな植物で構成されているんです。今日の散策が終わる頃には、街の見え方が少しだけ変わると思いますよ」
優しい口調でそう言うと、皇居の方向へ歩き出します。

10メートルほど歩いて足を止めたのは、駅前広場を覆うように敷かれた芝生。その脇でしゃがみます。
「見て、花が咲いています」
瀬尾さんの目線の先には、花なんてないような……と思った矢先、スプリンクラーの丸い装置のまわりに、米粒ほどの白い花を見つけました。
手持ちのカメラには顕微鏡モードがついていて、細かい構造がしっかり撮れます。観察のときの頼もしいパートナーだそう。

「小さいけれど、きれいな花ですよね。街中の雑草は、こうやってわずかに土がむき出しになっているところに生えるんですよ。人間の管理をすり抜けて、頑張って育つんです」
「見て、花が咲いています」
他にも、チドメグサやタンポポの仲間を発見。ただの芝生だと思っていた場所でも、よくよく見るといろんな形の植物があることに気づかされます。
なんだか見え方が変わってきたかも。普段目を向けていなかった小さな世界に、引き込まれていきます。
一度興味を持つと、とことん突き詰めたくなる性格
瀬尾さんが植物に強い関心を持ったのは、大学生のとき。「クローバー」によく似た「カタバミ」という植物の存在を知ったのが、興味の入り口でした。


当時よく観察していたのは、大学付近です。整備された通りなのに、目を凝らせばいろいろな植物が生えていました」
知識が少し増えたら、景色の映り方が変わったそう。そこから2年ほどで、目に入るだいたいの植物の名前がわかるようになりました。
「昔から好奇心が強いほうなんです。小学生の頃、やたら虫に詳しいクラスメイトがいませんでしたか? 僕は、まさにそのタイプ。興味を持つととことん突き詰めたくなるんですよ」

駅前広場から横断歩道を渡り、新丸ビルの脇へ。オシャレな雰囲気の石畳の隙間に、何かが生えているのを見つけました。
「これ、ナリヒラヒイラギナンテンですね。お母さんが横にいますよ」
真横には、腰ほどの高さの植木鉢。大きな葉をつけたその植物と、地面に生えた植物は、葉の形がそっくりです。

「このお母さんから種が落ち、石畳の隙間に着地したんですね。この子は、狭い隙間では育たないから、きっと来年あたりにはもう姿を消していると思います」
瀬尾さんの口ぶりには、植物への愛がにじみ出ています。
「お母さんの近くにとどまる種もあれば、風に乗って遠くまで飛んでいく種もあります。種類によって違いますが、飛距離はだいたい50〜100メートル。でも運がいいと500キロ飛ぶことあるといわれています」
子孫を残すために、いかに種を残すかが植物たちのミッション。他の個体との受粉が難しい場合は、自らの花粉を受粉する「自家受粉」で種を残すこともあります。
「自分だけが知っている」特別感がたまらない
皇居に続く小さな広場にやってきました。結婚式の前撮りをしているカップルを横目に奥に進んでいくと、また瀬尾さんが立ち止まります。
「このあたりに生えているのは、タマリュウという園芸植物です。でも、一部違う種類が混じっているのがわかりますか?」

高さの低い、芝生のような植物。一見、どれも同じですが、ときおり裏が白いものがあることに気づきます。
「裏が白いのは、チチコグサです。このふたつ、まったく違う種類なんですよ。チチコグサの白い部分をカメラで撮って拡大してみますね」
瀬尾さんのカメラには、細かい白い毛がびっしりと映っています。

「よく見ると毛なんです。水分が蒸散するのを防ぐ効果があると言われています。チチコグサは繁殖力が強く、一面に綿毛を飛ばして広がっていくんですよ。このあたりでは、タマリュウと陣地争いをしていますね」
一見同じに見える植物は、まったくの別モノ。秘密を知ったかのような、得意な気分になってきました。
「僕が観葉植物よりも雑草に惹かれるのは『自分だけが知っている』という感じがするからなんですよ。みんなが素通りしている景色でも、僕には特別に見える。それがうれしいんです」
皇居はもう目の前。瀬尾さんは、道沿いの植物に手を伸ばします。

「このネコジャラシのようなものが、今気になっているんです。先日もこの辺りで見つけたのですが、もしかしたらまだ日本で名前がついていない植物かもしれなくて。博物館に標本を送って、問い合わせているところです」
珍しい植物や、まだ見たことのない植物に出会えたとき、瀬尾さんはいちばんテンションが上がるそう。現在は3000種類ほどの植物を把握していますが、「まだまだ知るべきことは山ほどありますよ」と笑います。
「名前は知っていても、構造までは詳しく知らないという植物もたくさんあるので。本当に奥が深い世界だから、飽きることはありません」
東京のど真ん中で、数万個の種が飛び交う
皇居を囲む内堀通りに到着しました。
横断歩道の脇の地面、コンクリートの隙間をくぐるように10センチほどの草が生えています。

「これはオオアレチノギクです。きっとあそこの大群から飛ばされてきて、ここにやってきたんですね」
そう言って指をさしたのは、車が行き交う内堀通りの中央分離帯。腰ほどの高さのオオアレチノギクがゆさゆさと揺れています。

「あの大群の背丈と比べると、この個体はだいぶ小ぶりです。生育環境が悪いからですね。でも、これでもすでに成長しきっているはず……」
瀬尾さんが指先で先端に触れると、カサカサと音が。
「ほら、もう綿毛が出ていったあとですね」。

「お花一個で、数十個もの種ができるんですよ。こんなに小さくてもいくつも花をつけるから、合計1000個以上の種を飛ばすと思います。ちなみに、あの中央分離帯にある大ぶりサイズにもなると、飛ばす種は万単位です」
東京のど真ん中。こんなにダイナミックな種飛ばしが行われていたとは。目に見えない自然の活動が、身近に感じられます。
「植物に詳しくなると、信号待ちの時間すら楽しめます。街中を歩いていて、手持ち無沙汰になることがありません」
瀬尾さんは、植物観察を目的に旅行に出かけることも多いそう。
「同じ日本でも、場所によって植物のラインナップは大きく変わります。沖縄や離島は特に顕著で、時間を忘れて見入ってしまいますね。でも横浜の山下公園なんかは、近場なのに独特の種類を見ることができますよ」
横浜の港には、海外から来た荷物が集まります。トランクなどに付着していた種が地面に落ち、他ではめったに見ない植物が芽生えるそうです。
こうして、瀬尾さんとの1時間弱の散策が終了。瀬尾さんの目にうつる鮮やかな世界を垣間見ることができました。
「これをきっかけに、植物にちょっとでも目が向くようになったらうれしいです。コンクリートの隙間やフェンス沿いなど、僕らの生活圏内には多種多様な草花が生えています。これからぜひ、意識してみてください」
取材を終えて、一人歩く帰り道。今までこれっぽっちも意識していなかった足元の「緑」が、まるで違って見えるのでした。
***
執筆:安岡晴香
編集:三浦 玲央奈
撮影:持田薫