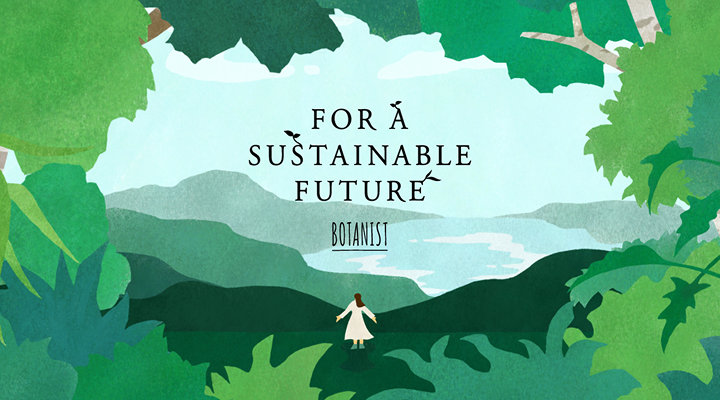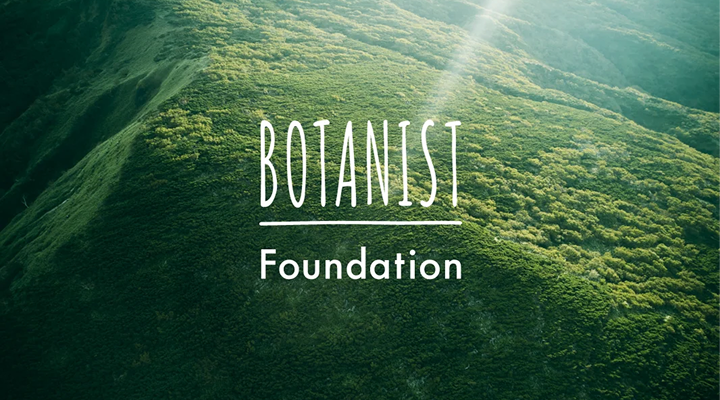SUSTAINABLE 24
多様性は可能性。命溢れる森づくりの意義
2025.09.25
植物と共に生きる未来のために。BOTANISTが進めるさまざまなアクションの中でも大きなものの一つに、多様性のある森づくりがあります。ではなぜ、森に多様性が必要なのでしょうか? そもそも多様性のある森とは何なのか? 森から多様性がなくなるとどうなる? その答えを追い求めて、長野県北部に広がる、とある森を訪れました。
人の手で甦らせた、多様性溢れる森。
多様性のある森とは、多種多様な動植物が生息し、生態系が健全に機能している森のこと。一見たくさんの木々が生い茂っている森でも、構成する樹種が単一であれば、多様性のある森とは言えません。
元々日本には、主要な樹木が500種類以上あると言われています。しかし戦後、薪として利用されていた広葉樹の価値が低下し、木材として利用しやすい針葉樹の価値が高まった結果、国内にはヒノキやスギを主とした単一樹種の人工林が数多く形成されました。さらに、それら人工林の中には木材伐採後に再造林されず、放置林として問題になっているものも少なくありません。
そのため近年、今後木材生産には適さない森や手入れの見込みがない森については、広葉樹も針葉樹も含めたさまざまな樹種が混在する、多様性のある森に生まれ変わらせていく必要性が叫ばれているのです。

そのような中で注目が高まっているのが、長野県の北端、信濃町の一角に広がる「アファンの森」。ここは国内でも指折りの多様性溢れる森として知られています。
実はこの森、かつて高度経済成長の波にのまれて40年以上放置された結果、ついには「幽霊森」と呼ばれるまで荒れ果てていた場所。1986年、そんな状況を目の当たりにした英国出身の作家で環境保全活動家のC.W.ニコル氏が、「日本本来の美しい自然環境を取り戻したい」と自ら土地を買い取って「アファンの森」と名付け、一から森づくりを始めて再生した経緯があります。
2002年には森づくりを未来につなげるため、一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団を設立。ニコル氏がこの世を去った後も、その想いは今に受け継がれています。現在、アファンの森財団の事務局長を務める大澤 渉さんによると、「アファンの森づくりのテーマは、たくさんの生き物たちが住める、生物多様性豊かな森を再生すること。それを、永遠の森として残していくことです」。
では、アファンの森はどのように再生を果たしたのでしょうか? まず、小鳥たちが好んで巣を作る茂みだけを残して、地面を覆う笹や藪などの草を刈り、今にも倒れそうに折り重なる木々を間伐。見通しが効き、陽の光もたっぷりと降り注ぐ、明るく風通しの良い空間に整備しました。そこへ、改めてこの土地に適した地域由来の木々を植樹、育てていったのです。
同時に、地面まで日光が届くようになったことで、草木が芽生え、花が咲き、昆虫や鳥が集まってくるように。そうして種が運ばれるようになると、また新たな植物が根付いていく。合わせて、池を掘ったり水路をきれいにしたり、水辺の環境が整えば、水辺の生き物も増える。生き物が増えれば、それらを捕食する動物たちが生息し始める……。という風に、あらゆる生物が共存できるよう、必要なものと妨げになるものを選り分けながら丁寧に手を入れていったことで、多彩な動植物がこの地へ還り豊かな森へと発展。現在は本来の森の生態系へと戻りつつあるどころか、絶滅危惧種とされている動植物も60種類以上確認できるまでになっています。
森の多様性が、人間の可能性を広げてくれる。
ところでなぜ、森には多様性が必要なのでしょうか? 大澤さんいわく「多様性があるというのは、色々な可能性があるということです」。
人間は、自然の中にあるさまざまなものを資源として利用し、生活しています。「だから、色々な生き物が存在したほうが、可能性は広がっていく。まだどのような機能や効果があるのか分かっていないものも含めて、たくさんのものが自然の中にあるというのは大事な要素だと思います」と、大澤さんは話します。
例えば、生きるために重要なものの一つである薬。今でこそ、化学的に有効成分を作り出して薬として販売しているものも多いですが、そういった技術がなかった昔は、木や草花、虫、鉱物など、自然の中にあるさまざまなものを薬として使っていました。何も分からない中で、何がどのような効果を持つのか色々と試しながら発見していった積み重ねが、現代の製薬につながっているのです。そして、多様性溢れる森の中にはきっと、まだ人間が見つけ出せていない“薬のもと”がたくさんあるのではないかと考えられています。
また大澤さんは、「やはり人が生活していく中で、さまざまな生き物に触れられることは、感性が豊かになることにつながります」とも。森林浴は心身の癒しになると言われますが、多様性のない森の中で活動するよりも、色々な植物や動物たちが暮らす、命溢れる森の中で活動するほうが、五感でたくさんの刺激を受けることになります。そうして、本来の自分を取り戻したり、新たな自分に出会ったり。豊かな森は、人の心も豊かに育み、可能性を広げてくれるのです。

多様性が失われた未来を想像してみる。
では、もし森に多様性がなくなると、どうなってしまうのでしょうか?
まず、森の多様性が失われるということは、そこに住む生き物同士の関係性が乱れ、途絶えることを意味します。例えば、ある植物が花を付けるのに必要な花粉を運んでいた昆虫が何かの拍子にいなくなると、その植物は子孫を残せず、やがて絶滅するでしょう。大澤さんは「自然界に単独で生きているものなどおらず、必ず何らかの関係性でつながっています。しかもただの連鎖ではなく、網目状に複雑に絡み合っていて、何と何につながりがあるのか、完全には分かりません」と言います。だからこそ、あらゆる可能性を断ち切らぬよう、多様な生き物が存在できる状態を保つことを大切にしているのです。
それを踏まえて大澤さんは、「森が多様性を失うことは、私たち人間がまだ調べきれていない自然の力を、知らぬ間に失うということ。人類にとって大きな損失です」と続けます。薬の例で言うと、今後たくさんの命を助ける“薬のもと”となったかもしれない植物が、誰にも発見されることのないまま絶滅するようなものです。
また、多様性が失われる過程で環境バランスが崩れると、大きな災害にもつながりかねません。大地に根差して生きる樹木の中には、降り注ぐ雨水を地中に蓄える機能を持つものがあります。もしその樹木がなくなれば、雨水は蓄えられることなく一気に地面を流れ、洪水になってしまいます。さらに、私たちの生活に欠かせない水は元を辿れば地面に蓄えられた雨水ですから、その蓄えがないとなると、雨が降らなければすぐに水不足になるといった事態も考えられるのです。
また、大澤さんは、「多様性がなくなると、間違いなく人間は生きていけなくなります」とも指摘します。さまざまな生物が存在し、色々な生き方をして成り立っている今の日本の環境は、長い年月をかけて構築されてきたものです。それが失われていくとすれば、どう考えても長い目で見た時に、人間にとって確実に大きな影響があると言うのです。
一方で、こうも問いかけます。「多様性がなければ、生きていてもつまらないものになると思います。植物に限らず、食べ物にも多様性があるおかげで、豊かに生活できている部分がありますよね。例えば『葉物野菜はレタスしかありません!』となると、バラエティがなくてつまらないでしょう? そういう意味でも、多様性は大切だと思います」。

多様性溢れる森を守る、BOTANISTの挑戦。
前述の通り、アファンの森は、人の手で甦らせた森。一度多様性が失われてしまっても、その大切さに気づいてしっかりと手入れをしていけば、再生することができるのです。
BOTANISTも2021年より、北海道美幌町にあるカラマツの伐採跡地を植生回復し多様性のある森に戻す「BOTANISTの森」プロジェクトを進めています。
また、2023年に設立した一般財団法人BOTANIST財団では、植物の多様性を守り、持続可能な共生社会の実現に向けた活動を行う団体を対象とした助成金プログラムを開始。2024年度はアファンの森財団を含めた2団体、2025年度はさらに2団体を加えた計4団体を助成先として決定し、協働しています。
植物と共に生きる、豊かな未来のために。
多様性溢れる森をつくり、守るBOTANISTの取り組みは、これからも続いていきます。